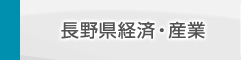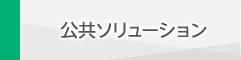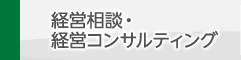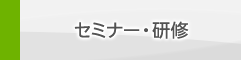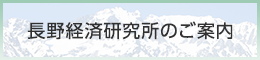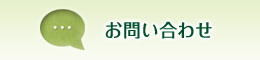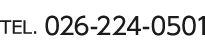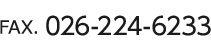松本空港の国際化に向けた現状・課題<2025.7.11>
開港60周年を迎えた松本空港
県営松本空港(松本市・塩尻市、愛称・信州まつもと空港。以下、松本空港という)は、1965年7月に開港し、2025年に60周年を迎えました。これまで松本空港は、国内定期路線の運航を中心に利用促進を図ってきましたが、グローバル化が進む中で、インバウンドの受け入れや国際交流をより活発化させるためには、国際化が不可欠だと考えます。県も、16年に公表した松本空港の今後の取組方針の1つに国際化を掲げています。
そこで以下では、松本空港の国際化に向けて重要なポイントとなる、ハード面や運用面などの主な現状・課題についてまとめてみます。
国際化に向けた現状・課題
(1)【滑走路】松本空港の滑走路は現状2,000mですが、地方空港で一般的な国際定期便に使用される小型ジェット機(座席数140~160席)の運航には標高等の立地条件を考慮すると2,700m程度が必要とされます。しかし、用地確保や住民生活・産業活動への影響、騒音影響などの課題が多く、県によると当面は現滑走路の活用により、空港の活性化に取り組む方針となっています。
(2)【航空機材】現状の滑走路の長さでは、リージョナルジェット機(座席数50~100席)の運用に制限されます。小型ジェット機を運用する際には重量制限が必要となり、搭乗人数や搭載する燃料の量を制限しなければなりません。搭乗人数を制限すれば運賃収入も減り、燃料が少なければ途中の空港で給油をすることなりコストが増します。従って、チャーター便によるスポット運用なら対応できても、継続的な定期運行便では採算面が課題となります。
(3)【国際線対応設備】県は入国審査等を実施するためのCIQ(税関・出入国管理・検疫)施設を24年10月に新たに設置しました。従来は国際チャーター便の到着の都度、空港内を簡易的に区分し、臨時的な設備で対応していましたが、新施設の設置により入国者の動線が確保されるようになりました。しかし、それぞれの業務に当たる人員は常駐していないため、市外・県外の各機関から派遣を受けています。今後、国際チャーター便や定期便を増やす際にはこうした専門人員の定期的な確保・調整が重要な課題になります。
(4)【人材・運用面等】人材面では、地上サポート業務を行うグランドハンドリング人員などを含む空港職員の確保が必要となります。また、運用面では就航先空港や海外航空会社との連携、地元自治体や民間事業者との連携、二次交通や駐車場の拡充など、多岐にわたる対応が求められます。
国際化を目指す上では、上記のような困難な課題に長期的な視野で当たっていく必要があります。まずは、年間約数便~数十便にとどまっている国際チャーター便の受け入れを年100便程度に増やして実績を重ね、地元地域の理解も得ながら、本格的な国際化を目指すことが望まれます。

松本空港に新たに設置された入国審査等を行うCIQ施設
※ 松本空港の国際化については、経済月報2025年7月号掲載の調査レポート「松本空港の国際化について考える」で、同空港の現状や課題のほか、富山空港(富山県)、佐賀空港(佐賀県)、帯広空港(北海道)といった地方国際空港の国際化への取り組みを交えて詳しく紹介しています。ぜひ、ご覧ください。
関連リンク
産業調査
電話番号:026-224-0501
FAX番号:026-224-6233