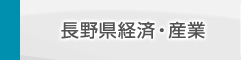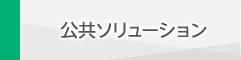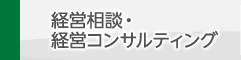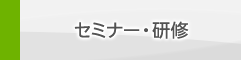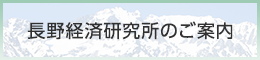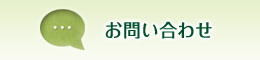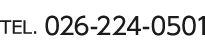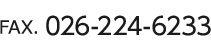社長のダメ出し、部下の指示待ち~ダメなのはどっち?<2025・07・11>
社長のダメ出しで「考えるだけ無駄」
仕事柄、多くの経営者や幹部と接する機会があるが、最近ある企業の幹部の方からこんな話しを聞いた。
「うちの社長は非常に優秀だが、それゆえに部下の話を最後まで聞かず、すぐにダメ出しをする。だから社内には『考えるだけ無駄。社長の言う通りに従っていた方が無難』という空気が蔓延している」と。
確かに、このような状況下では、部下が余計な事を言わず、社長の指示に従うのは合理的な選択だ。しかし、この合理性は組織に深刻な弊害をもたらしてしまう。
部下は、何を提案しても否定され、評価されないという経験を重ねることで、「どうせ社長の言う通りにしかならない」となる。こうした心理的な萎縮が進むと、部下は自ら考えることを止め、「指示待ち人間」になっていく。そして次第に、主体性を失い、挑戦を避けるようになる。
挑戦することが評価されないのなら、現状維持が最も安全と考えて当然だ。
「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」
この話を聞いて、ふと思い出したのが山本五十六の有名な格言である。「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」。
今さらながら、実に的を射た言葉だと感心させられる。多くの社長は「やってみせ」「言って聞かせる」までは実行している。しかし、先の企業のように「させてみせ」が欠けてしまいがちなのである。
部下に「させてみせ」なければ、成長するわけがない。結果として、社長の能力を超えることのない、社長に依存した脆弱な会社に陥ってしまう。
優秀な経営者ほど、「自分でやった方が早くて正確だ」と頑張ってしまう。特にオーナー企業の社長は、自ら築き上げた会社への強い自負があるため、成功体験から離れることが難しい。
その結果、社長がすべてを判断し、指示を出す構造が固定化してしまう。こうした構造の中、繰り返しになるが、部下は「どうせ自分の意見は通らない」「考えるだけ無駄」と、自ら考え、挑戦する意欲を失っていく。そして、そんな空気が組織全体に蔓延していく。
このような悪循環を断ち切るためには、「させてみせる」覚悟が不可欠なのである。自ら考え、実行し、試行錯誤するプロセスが、部下にとっても組織にとってもかけがえのない成長の機会となる。
「ほめてやらねば」でやりがいと成長を
そして、忘れてはならないのが「ほめてやらねば」である。
部下が自ら動き、挑戦した結果、たとえ小さな成功であっても、それを上司が認め、言葉にして称えることは極めて重要だ。人は承認されることで、自分の行動に意味を見出し、次なる挑戦への意欲を高める。これは単なるモチベーションの話ではなく、仕事に対する「やりがい」や「自己肯定感」を育む根幹である。
「褒める」ことは、部下の成長を促す最もシンプルで効果的なマネジメント手法の1つだ。にもかかわらず、意外にそれを実践する経営者は少ない。「褒めると何かが減る」とでも思っているかのようだ。
言うまでもなく部下を褒めると減るどころか、部下のやる気は増し、組織全体のエネルギーは高まり、挑戦する風土が生まれる。人は「認められる場所」でこそ、最も力を発揮するのだ。
やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば・・・人は動かないし、会社も成長しない。
(初出)SBCラジオ 飯塚敏文のあさまるFriday 2025・7・11放送
関連リンク
産業調査
電話番号:026-224-0501
FAX番号:026-224-6233