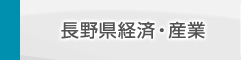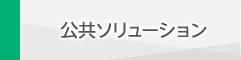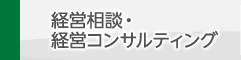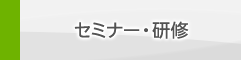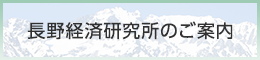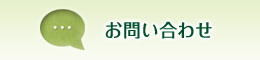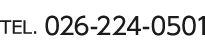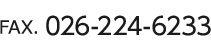長野県内で再び増加傾向にある松くい虫被害<2024.11.25>
森林政策の課題となっている松くい虫被害
長野県は森林づくりや里山整備などの森林政策を進めていますが、その中で以前からの課題の1つに松くい虫の被害があります。実は、県内の被害量は2013年度をピークに減少傾向にあったのですが、最近の2年間は続けて微増しており、対策が求められています。
今回は、この松くい虫被害について、これまでの経緯や行政の対応策などをご紹介します。
松くい虫被害の原因は線虫とカミキリ虫
そもそも、松くい虫被害とは「マツノザイセンチュウ」という体長0.6~1.0mmの線虫が松の木の中に入り込むことで、松が水を吸い上げる働きが阻害され、枯れてしまうことを言います。このマツノザイセンチュウは北米原産で、明治時代に輸入の時に使われる梱包材などと一緒に国内に持ち込まれたとされています。ただ、この線虫は自分では松から松へと移動できません。それを助けているのが、「マツノマダラカミキリ」というカミキリ虫です。このマツノマダラカミキリは枯れた松の中で卵から孵化して成虫になるのですが、その際に松の中にいた線虫がカミキリに乗り移ります。そして、健康な松へ飛び移って樹皮を食べるカミキリと一緒に線虫も移動し、カミキリが食べた松に線虫が入って木を枯らし、その枯れた松にカミキリが卵を産み、孵化してまた線虫と一緒に移動するというサイクルを繰り返し被害が広がっていきます。
この松くい虫被害は国内では1905(明治38)年に長崎県で初めて発生し、73(昭和48)年に原因が明らかにされました。そして、長野県内では81(昭和56)年に最初の被害が確認されてから増え続け、2013年度に約7万9千立方mと過去最大の被害量を記録しました。その後は対策の効果もあって減少傾向にありましたが、22年度に増加に転じ、23年度もさらに微増して被害量は約5万5千立方mとなっています。
また、県内でも地域によって被害状況に違いがあり、ここ20年ほどは松本の周辺で被害が急増し、県内の被害量の半数近くを松本地域が占めています。車で長野自動車道を走っていて、山間に近い東筑摩郡の麻績村や筑北村の辺りで松枯れの様子を間近に見たことのある方も多いと思います。
増加の背景には温暖化が考えられる
減少傾向にあった松くい虫被害が増加に転じた背景には、気候の温暖化が関係していると考えられます。線虫の運び役となるマツノマダラカミキリは松の木の中で冬を過ごすのですが、暖冬の影響で越冬しやすくなっているようです。また、夏の暑さで行動が以前より活発化していることも考えられています。被害に合う松林の標高も、これまでは高くて800mくらいまでだったのが、最近は1,000~1,100mほどの高さまで拡大してきており、気候の変化が松くい虫にとってより都合の良い環境を作り出してしまっていることが伺えます。
松くい虫の防除については、これまでも薬剤の散布や討伐駆除などさまざまな対策が取られてきました。さらに県は、被害状況や地理条件などに応じて、しっかりと守るべき松林を見極めてその周辺を重点的に防除するほか、被害の少ない地域に広がらないよう計画的に拡大防止策を進めていく方針です。また、地域の防災や減災にも関わる里山整備については、「長野県森林づくり県民税」なども活用し、従来のアカマツから松くい被害の及ばない広葉樹へ樹種を更新する取り組みも増やしていく意向です。
県内の森林を維持していく
長野県内は面積の約8割を森林が占めており、都道府県別の森林面積でも北海道、岩手県に次いで全国で3番目に多いまさに「森林県」です。森林は大切な資源であり、木材としての活用だけでなく、生態系や地球環境保全のほか、土砂災害の防止や水質浄化などさまざまな機能を持ち、私たちの暮らしに必要不可欠な存在です。松くい虫被害への対応もそうした森林を維持していく重要な取り組みであり、これからも注目していければと思います。
2024年11月25日放送 SBCラジオ「あさまるコラム」より
関連リンク
産業調査
電話番号:026-224-0501
FAX番号:026-224-6233