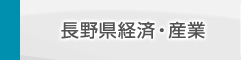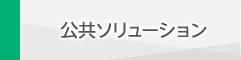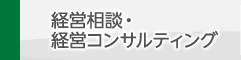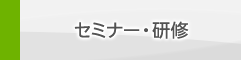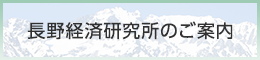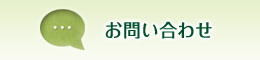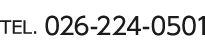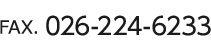地域連携で新産業をつくる―公立諏訪東京理科大学<2024・11・3>
地域貢献をミッションに2018年に公立化
公立諏訪東京理科大大学は、1990年に私立東京理科大学諏訪短期大学として開学した。
2002年に諏訪東京理科大学として4年制大学に移行。18年には、諏訪地域6市町村からなる諏訪広域公立大学事務組合が公立大学法人公立諏訪東京理科大学を設立し、同大学が開学した。
「地域に一層貢献する大学」そして、「新しい産業の創出を通して、地域と我が国の将来の発展に貢献する」などをミッションに地域との連携に力を入れている。
産学連携で挑戦をする亜鉛を使った燃料電池
水素を使った燃料電池車では、水素を補填すればすぐに走れるというのは大きな長所だ。
しかし、水素は値段が高額であり、車輛で使う場合には高密度・高圧で貯蔵しなくてはならない。そこで、常温常圧で扱える金属材料である亜鉛に置き換えることで安全に扱える燃料電池となる。
同大学の小川 賢准教授は、この亜鉛を使った燃料電池の開発に向け、下諏訪町の大和電機工業株式会社と連携し、小さな銅の球に亜鉛でめっきをした「亜鉛ビーズ」という電池の材料を開発した。現状では、リチウム電池に対して容量が理論的には3~4倍となるため、容量を抑えた上でエネルギー容量を達成できるよう研究を重ねている。
地域企業の新規事業展開に寄与
同大学と連携して新事業開発に向け活動を続ける大和電機工業(株)は、番組内で同大学が地域連携に力を入れていることの恩恵について以下のように語っている。
「大学の持っている技術やノウハウ、設備を我々も活用させていただくことは非常に有用で、逆に大学のこれらの助けがないと自社独自で新しい事業を展開していくということはなかなか難しいのが実態です。諏訪東京理科大学は地域連携に非常に力を入れていただいており、そういう大学が我々の地元にあるっていうのは我々中小企業にとっては非常にありがたい環境です。」
大学にとっての地域連携のメリット
一方、大学にとってのメリットについて、小川准教授は以下のように述べている。
「この諏訪地域は中小企業が多いので、まずは社長とすぐ話ができ、製品のイメージの議論ができることが大きなメリットです。大学の基礎研究だけですと、基礎的なところの研究はできますが、それ以上は難しいものです。地元企業と話をすればすぐに製品に近い形ができますので、かなりスピーディーに社会実装できる形に持っていけます。」
Win- Winの関係で広がる産学連携
産学連携については、盛んになり始めた頃「大学と企業では見ている紙が違う」といる話を聞いた事がある。「大学が見ている紙は学術論文で、企業が見ている紙は紙幣」ということらしい。同床異夢の中、噛み合わないといった時代があった。
紹介した事例は1つだが、諏訪圏で見られる産学連携はWin- Winの関係を深めている。
そのような産学連携であれば、持続的に広がっていくだろう。
同大学の公立化の効果も、そのような場面で見えてくるように思う。
(資料)SBC「明日を造れ!ものづくりナガノ」(2024年11月3日)
関連リンク
産業調査
電話番号:026-224-0501
FAX番号:026-224-6233