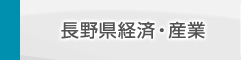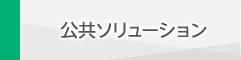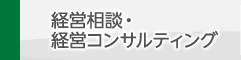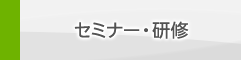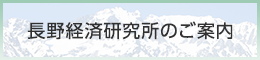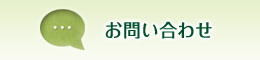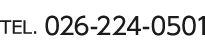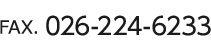人を大切にする経営で元気をつくる(13)-セラテックジャパン<2024・10・30>
MPSブランドが可能にする非価格競争
セラテックジャパン(株)は、特定の資本系列に属さない独立系のファインセラミックス加工メーカーだ。そして、単なる下請加工業ではなく、取引先に対し提案を行い、高い付加価値を創出する「ソリューションサービス業」として成長してきた。こ れ を MPS(Material ProcessingService)とネーミングすることで、他社との差別化を図りブランド化に成功している。
高い実績に裏打ちされたMPS ブランドが、「セラテックジャパンのMPSなら大丈夫」「セラテックでなければ」という顧客の信頼を形成し、価格競争とは一線を画した非価格競争を可能にしている。
アメーバ経営導入のメリットとデメリット
MPSとの両輪で、同社を支えてきたのがアメーバ経営だ。1994年に京セラ(株)からコンサルティングを受け、導入をしたものである。
アメーバ経営は、大きな組織を小集団(ミニカンパニー)に分け独立採算で運営をする仕組みで、カンパニーごとの業績も毎月、全社員に公表される。これにより、経営者はカンパニーごとの収益状況や課題を細かく把握することができ、各カンパニー同士が競い合うことで、業績がより向上することも期待できる。
しかし、一方でカンパニー同士の競争関係が強くなりすぎると、セクショナリズムが発生し、社内の人間関係が悪化してしまうことがある。それ故に導入後数年でアメーバ経営を止めてしまう企業も少なくない。
同社でも、導入後しばらくしてから同様の問題に見舞われ、まとまりを欠いた社内環境に悩まされることになった。
一体感回復のための秘策その1「委員会制度」
しかし、このような苦難を経験しても、同社はアメーバ経営を続けている。それは、メリットを生かしながらもデメリットを解消する方法を、苦い経験から見いだしたからである。
同社では、製造部門を、磁器加工、精密加工、精密研磨など10の部署に分けており、それぞれを独立採算制のカンパニーとしている。これらは現在、共に協力し助け合える、まさに「オールセラテックジャパン」と呼ぶにふさわしい組織に生まれ変わっている。
その秘策の1つが、委員会制度である。委員会制度は、改善提案委員会、環境整備委員会、いい会社にしよう委員会など10の委員会からなり、それぞれが各カンパニーのメンバーから組成される混合部隊となっているため、縦割りとなっているカンパニーに横串を刺す活動となっている。
秘策その2「コミュニケーション補助金制度」
秘策の2つ目は、コミュニケーション補助金制度で、先の委員会制度を活用して作り上げたものだ。
社内の仲間意識を高め、お互いの信頼関係を築くためには、コミュニケーションが欠かせない。そのための補助金を会社が用立てる制度である。
改善提案や環境整備はそれぞれの委員会で評価をしているが、評価に応じた報奨金がコミュニケーション補助金という形で支給され、それを社員の交流を図るコンパ等に使うことができるようになっている。
社員の声をとことん聞くオピニオンサーベイ
デメリットをはらむアメーバ経営を強みにしているからこそ、社内を横断するコミュニケーションの円滑化は会社の生命線と言え、同社の経営はそこに重点を置いてきた。
併せて、経営者と社員との縦のコミュニケーションにも力を入れ、毎年、オピニオンサーベイを実施している。オピニオンサーベイで出される要望・意見は100~200にも上る。これら全てに対し、四半期ごとの方針勉強会の場で平林明社長が1件1件読み上げ、それぞれに対する会社の対応を発表し、できることは極力実施し、社員の納得を得ている。
「社員が喜びや生きがい・やりがいを感じて働くことができなければ、お客さまを喜ばせることはでません。そのため社員が働きやすい職場環境形成には最も力を入れているのです」と平林社長は語っている。
リファラル採用を導入、母親を入れたくなる会社
このような会社の風土であればこそ、同社はリファラル採用で成果を上げることができている。同社は21年に同制度を導入した。リファラル採用とは、自社の社員からの紹介による人材の採用のことである。
同社のリファラル採用の実績は、これまで20名を超える人数となっている。友人・知人が10名弱、甥3名、義弟1名、義姉1名、弟2名、妹1名、息子5名、娘2名、そして母親2名という属性だ。自分の子供を入れたい会社は間違いなく、いい会社だ。そして、自分の母親を入れたい会社はもっといい会社に違いない。誰よりも大切な母親に「ウチの会社いいよ、働いてみる?」。このような言葉を掛けることが、一般的にできるだろうか。
自分の勤めている会社を友人やましてや家族に勧められるということは、相当にエンゲージメントが高くないと難しい。
人手不足の時代、高いエンゲージメントが必要な時代になっている。
(資料)『社員を大切にする経営で元気をつくる』長野経済研究所「経済月報2024年10月号」より抜粋
関連リンク
産業調査
電話番号:026-224-0501
FAX番号:026-224-6233