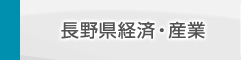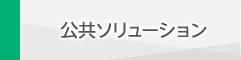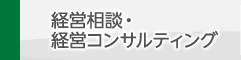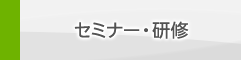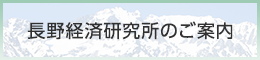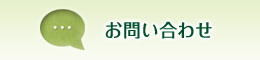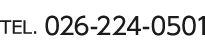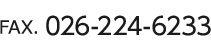休暇について考える<2024.8.27>
休暇が多い8月
2024年のお盆は日並びが良く、「山の日」を含む3連休後にお盆の期間が続いたため、元々土日祝日とお盆が休業の職場であれば、8/10(土)から8/18(日)まで9日間の連休になったと思います。また、お盆の期間が休業でない職場でも、個人的に有給休暇などを取得した方も多かったのではないでしょうか。
この様に8月は休暇を取得する機会が多いということで、今回は有給休暇など職場の休暇に関する話題を紹介したいと思います。
有給休暇とは
まず、有給休暇について簡単に説明します。年次有給休暇の付与日数は労働基準法で決められており、正社員やパートタイムによる区分はなく、勤続年数や所定労働日数によって異なります。通常、フルタイムの労働者で勤続年数6年半以上であれば年間20日が付与されます。
有給休暇の取得については、働き方改革関連法案の施行により、2019年4月から「年10日以上の有給休暇を与えている従業員には、5日以上の有給を取得させる必要がある」とされ、年次有給休暇の取得が義務化されました。従って事業所には、従業員に最低でも年に5日間は休暇を取得させる義務があり、守れないと罰則や労働基準監督署による指導の対象となります。このため、各事業所では従業員が確実に有休を取得できるよう管理する必要があります。
国内企業の休暇制度の状況
以下では、厚生労働省「令和5年就労条件総合調査の概況」をもとに、国内企業の休暇制度等の状況について紹介します。まず、今では一般的になった「週休2日制」を採用している企業は85.4%でした。ただ、そのうち「完全週休2日制」は53.3%で、隔週や月2回など完全ではない週休2日制が32.1%となっています。特に従業員数の少ない企業ほど完全週休2日制の割合が低い傾向にあります。
年次有給休暇については、年間の労働者1人の平均付与日数は17.6日で、平均取得日数は10.9日でした。こちらも、従業員規模が小さい企業の方が若干少なくなっています。また、産業別にみると、「卸売業・小売業」、「宿泊業・飲食サービス業」、「教育・学習支援業」で、有給休暇の平均取得日数が10日未満となっています。先ほどお話しした通り、勤続年数や所定労働日数によって有給休暇の日数は異なるものの、こうした業種では、元々業種柄休みが取りづらいことに加え、最近は人手不足などもあり、有休の取得が伸び悩んでいると考えられます。
このほか、年次有給休暇などの法定休暇以外に「特別休暇」を就業規則等で制度化している企業が全体の55.0%に及びました。内訳は、「夏季休暇」が最も多く37.8%、次いで「病気休暇」が21.9%となりました。また、全体における割合は数%と少ないものの、「ボランティア休暇」や「教育訓練休暇」などを定めている企業もあり、ワーク・ライフ・バランスや人材育成の観点から多様な休暇制度を設けて働きやすい環境作りを進めることも大切だと思います。
休暇制度の有効活用に向けて
以前から日本人は勤労意識が強く、仕事を休まない傾向が強いなどと言われています。確かに有給休暇の取得日数を欧州の国々などと比較すると日本は10~15日ほど少ないのですが、一方で祝日の数は国際的にも多い状況にあります。従って他国と比べて決して休んでいない訳ではありませんが、まとめて長期の休暇を取るといった習慣がなく、「休み下手」な印象です。
そうした中、例えば従業員数の少ない企業でも、経営トップが率先して社員に休暇の取得を呼び掛けたり、人事担当者が休暇制度の説明を丁寧に行ったりすることで、職場の雰囲気が変わり、休暇取得率が増加した事例もあります。ぜひ、心身を健康に保ち元気に仕事をしていくためにも、休暇制度の設定だけにとどまらず、有効な活用が進むことを期待したいと思います。
2024年8月26日放送 SBCラジオ「あさまるコラム」より
関連リンク
産業調査
電話番号:026-224-0501
FAX番号:026-224-6233