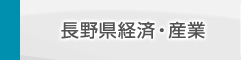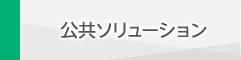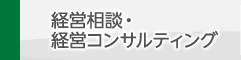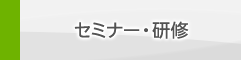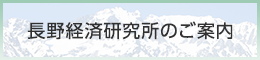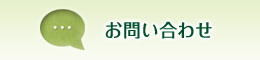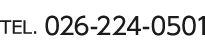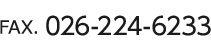コロナ禍前を上回るも低水準にとどまるスキー場利用動向<2024.5.27>
県内主要22カ所のスキー場利用動向調査
長野経済研究所では毎年、長野県内の主要なスキー場にご協力いただき、各シーズンのオープンから3月末までの利用動向を調査しています。現在県内には約80カ所のスキー場がありますが、当研究所が調査対象としている22カ所の利用者数の合計は、県内スキー場利用者数全体のおよそ7割に相当しています。
今回は2023年度シーズン、つまり23年11月以降のオープンから24年3月までの各スキー場の利用動向について調査結果がまとまりました。
前年度まではコロナ前の水準に届かず
まず、これまでの利用者数の推移について簡単にご説明します。当研究所では1992年度からこの調査を開始しているのですが、その92年度の利用者数が1,423万人とピークでした。その後は年々利用者数が減少していき、2010年度に464万人と初めて500万人を割り込みました。ただ、その後は下げ止まりがみられ、概ね500万人前後での推移が続きました。
ところが20年度(20年-21年)はシーズンを通して新型コロナの影響が大きく及び、調査開始以降で最低の268万人となりました。翌21年度、22年度と徐々に回復しましたが、コロナ前の水準には届いていませんでした。
コロナ禍前を上回るも雪不足等により低水準にとどまる
そして今回、23年度は前年度より3.6%増の延べ445万5千人となり、コロナ前の19年度(438万人)を上回りました。ただ、それでも雪不足などの影響もあり、当研究所の調査開始以降では5番目に低い水準にとどまりました。
各スキー場の動向をみると、22カ所のスキー場のうち半数以上の13カ所で利用者数が前年度を上回りました。中でも白馬村などの大北地域ではシーズンを通して集客が安定し、調査対象となっている5カ所のスキー場全てで前年度に比べ二桁増となりました。
一方、山ノ内町や野沢温泉村などの北信地域では、二度の3連休があった2月を中心に個人や学校関連などの団体利用が伸びましたが、シーズン序盤の12月や終盤の3月に雪不足が生じたことなどから、シーズン全体の利用者数は前年をわずかに下回りました。
さらに、中・南部地域のスキー場も、特に12月、1月にまとまった降雪が少なく雪不足の状態にあったことから多くのスキー場で前年度を下回りました。また、これらの地域の中には、シーズン途中でゴンドラやリフトなど設備の不具合が発生し、一時的に稼働率が低下したり、休業を余儀なくされるスキー場も散見されました。
このように、今年度は利用者数が回復傾向にあった一方で、雪不足の影響に加え、各スキー場における設備の維持・メンテナンスの重要性を改めて認識させられる調査結果となりました。
なお、今年度は燃料価格や電気料金、人件費等の上昇を受け、リフト券の価格を値上げするスキー場が多くみられました。ただ、さまざまな物の値段が上昇している中で、価格転嫁に対する消費者の理解が進んだこともあり、誘客への影響は限定的だったようです。
外国人利用者のさらなる誘客に向けた対策も重要
外国人利用者については、多くのスキー場で前年度に比べ増加しました。全体的に、中国・香港・台湾・東南アジアなどアジアからの利用者が増加傾向にあったほか、大北・北信地域を中心にオーストラリアや欧米地域からの利用者も増えました。この要因としては、コロナ禍からの回復に加え、円安が進行したことも外国人利用者の誘客を後押ししたとみられます。
こうした外国人利用者は、今後さらに増加が見込まれます。外国人の誘客を強化するスキー場では、海外向けの営業活動や情報発信のほか、海外からも事前にインターネットを通じてリフト券の購入・決済が完了できるようシステムを整備するなどの対策が重要と考えられます。
今回の調査結果の詳細は当研究所のホームページ「2023年度県内主要スキー場利用動向調査(速報)」にも掲載しています。また、経済月報2024年6月号にもレポートを掲載しますので、ぜひご覧ください。
2024年5月27日放送 SBCラジオ「あさまるコラム」より
関連リンク
産業調査
電話番号:026-224-0501
FAX番号:026-224-6233