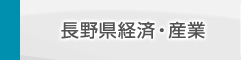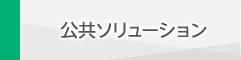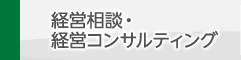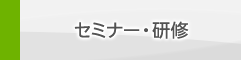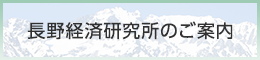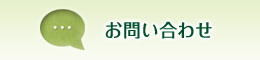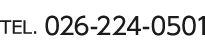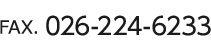物価高 もったいないを 思い出し・・・<2024・05・10>
止まらない物価高、負担が増す家計
長野県が4月19日に公表した、長野市の消費者物価指数の総合指数は、2020(令和2)年を100として108.7となり、前月比は0.2%上昇した。また、前年同月比も2.9%上昇し、31か月連続で前年同月を上回った。2年半物価が上がり続けている。
長野経済研究所が県民を対象に実施している消費動向調査(2024年1月)でも、物価に対する意識として、「高い」が49.2%、「やや高い」が46.1%と両方を加えた「高い」の回答割合は95.3%と9割を超えている。また、物価上昇に伴う家計支出の変化は、「物価の上昇により支出が増えている」が64.5%となっている。
ほとんどの家計が物価上昇を痛感する中で、6割の家計では支出が増え負担が増している。
無駄なモノを買わずに、できるだけ長く使う
物価高に対し我々にできることは何か。
同調査で最近の消費行動の変化を尋ねると、「必要なものだけを買い、無駄なものは買わないようになった」が58.5%と最も多く、次いで「できるだけ安い店で買うようになった」が32.8%、「同じ店でより安いものを買うようになった」が28.7%となった。
つまり、無駄なものを買わずに、買う際には出来るだけ安くという行動が増えているようだ。
さらに、このような消費行動の先にある対応を考えてみるなら、「買ったものは出来るだけ長く使う」、「安易に捨てることなく再利用する」などとなろう。
無駄なものは買わずに買ってからはできるだけ長く使う、これが物価高に対する消費者の定石だ。
物価高で改めて考え直す、捨てないということ
消費者の定石・・・既視感のある光景のように感じた。それは田舎の親の生活だ。
余計なものは買わないし、ものを捨てたところを見たことがない。
卑近な例としては、容器包装類だ。全て捨てることはなく、洗い再利用していた。包装紙も再度使うか、それでも余れば小さく切ってはメモ帳にしていた。
笑い話のようだが、食品用ラップフィルムも、あんな薄いものを洗って乾かしては再利用していたし、「使い捨て」と表示された台拭きなども、相当に汚れない限りは「使い捨て」ない。洗えば再利用できるのだ。
貧乏性の習い性と半分呆れて見ていた光景が、今ではところどころで見られ始めている。
改めて考えてみるなら、特段物価高だからということではなく、そもそも生活はこうあるべきだろう。大して必要でもないものを買っては、直ぐに捨ててしまう生活はまともではない。
「もったいない」ふたたび
親の口癖は「もったいない」だった。
語りつくされたエピソードだが、環境分野で初のノーベル平和賞を受賞した故ワンガリ・マータイさんが、ものを捨てずに使うなどを推奨する3R(リデュース・リユース・リサイクル)を一言で言い表せると感銘した言葉が「もったいない」だ。
物価高への対応として「もったいない」の重要性に気付く訳だが、優れた環境対応のキーワードとしてもマータイさんに見出されていた。今で言うならSDGsに欠かせないキーワードとなろう。
物価高に喘ぐ日々が続いている。
しかし、こんな中だからこそ、災い転じてではないが「もったない」を基軸に、少々まともからズレていた生活を考え直してみたい。
(初出)SBCラジオ あさまるコラム 2024.5.10放送
関連リンク
産業調査
電話番号:026-224-0501
FAX番号:026-224-6233