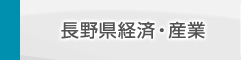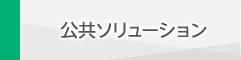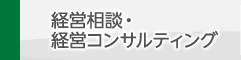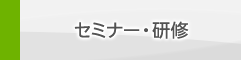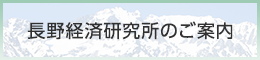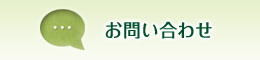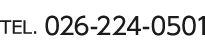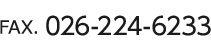共同研究(機械総合実習用教材の開発)
共同研究(機械総合実習用教材の開発)
| 連携企業 | 期間 | 参加生徒 |
| 不二越機械工業株式会社 | 平成20年4月~平成21年1月 | 機械科3年 14名 |
研究の目的
機械分野の技術者として将来活躍できる人材を育成するため、企業で行われているような一連のものづくりを授業の中で実践していく。機械装置を開発し作り上げるという内容を授業に盛り込むことで、幅広い分野、内容を関連づけて、ものづくりを経験させることができると考え導入した。
生徒が機械装置を開発していく中で、電子機械や産業機械について理解するとともに、それぞれに関連する部品についても幅広く学習することができる。更に、設計、製図 、加工、組み立てといった幅広い分野を一連の流れとして経験することで各分野の連携やそれぞれの技術について関連性をもって学習できる授業ができると考えている。また、今回の授業では幅広い分野を関連づけて扱うことから、他の授業での経験や学習内容、効果など互に大きく影響してくる。そのため、現在の学習内容では不足してしまい、 改善が必要となる部分が見付かることも予想される。その部分を授業改善として授業に反映していくことで、高校生にあった授業の再構築につながると考えている。
研究内容
<総合実習装置の開発>(電子機械)(課題研究)
総合実習装置を参考に、各自で仕様を決定し開発を進める。装置の完成を目指し、(1)設計、(2)製図、(3)加工、(4)組み立てといった流れで進めていくが、事前学習として各分 野の学習が必要となる。(1)設計では基礎知識としてコンベアに使用されているモータやセンサといった電子機械分野の学習やベアリングなど各種部品も同時に学習し理解を深めながら設計を行っていく。(2)製図では、CADを使い構想図、全体の組み立て図、部品図を作成していく。構想図では電子部品や機械部品などの形状も反映しながら作図を行い、部品の規格について学習しながら作図を行う。完成した構想図から全体図、部品図を作成する。全体図、部品図の整合性を確認するため検図を繰り返し行う。(3)加工、(4)組み立てでは、部品図をもとに部品の加工、組み立てといった部分も経験していく。作成する部品図に間違いや不具合があった場合は、関係する全ての図面に修正を反映する。完成した機械を実際に動かしその性能を仕様と比較し確認する。また、設計計算書、仕様書という形で報告書の作成も予定している。
<企業での総合実習装置の組み立て実習>(課題研究)
総合実習装置を開発していくなかで機械装置の機構や部品についての知識や組み立て作業といった経験が必要になってくる。そのため、機械装置を実際に使い具体的に構造を理解するため企業に行き実習を行った。実習の事前準備としてコンベア部分やエアー部分の機構や部品、部品図や配線図など製図についても学習を行った。企業では組み立て作業を中心に行い、その中で、装置の機構や部品についてさらに学習を深めて行き実習を進めることができた。企業の持つノウハウと技術者からのアドバイスを参考に実習を行うことができた。
実習結果
ベルトコンベアを開発する授業では、「学習内容を理解し興味を持つことができた」と答えた生徒が約80%いた。全体図や部品図を作図するといった製図の部分に抵抗があ るようで、「製図がにがて」「CADに時間がかかった」という回答が約50%あった。
また、生徒の感想では「部品の知識を学習することが大変だ。」といった意見も多かったが、その反面、「ベアリングが分かった」など部品について興味を感じるコメントも多かった。部品についての理解は進んでいるようだが全体図を作図するのに苦労しているようだ。装置の機構を考え作図していく中で、企業に伺い組み立て実習を経験してい る生徒の装置や部品に対する理解が早く、開発も進んでいるように感じる。
考察
実習中の様子から、テーマに興味、関心をもって取り組めているように感じた。今回の実習で、ある程度の手応えを感じることができた。多くの生徒が開発という幅広い分 野を経験し、実践的な知識や技術を身につけることができた。実施方法、時間的に課題が残るが、改善点として考慮していきたい。図面の作成に苦手意識を持っている生徒が予想以上に多く、作業の中でも見ることができた。
教材として総合実習用装置の導入が適切だったか課題は残るが、講義形式の授業と実習形式での授業を連携することや、幅広い分野について学習を盛り込めたことは生徒か らの反応から見ても成果があったといえる。今後、装置の完成と性能試験を行っていくが授業の内容や教材、生徒の反応など含め、総合的な成果を検討していくことが必要と考えている。
今後の活動
今回、実施した部分について不足し、課題となった部分について授業の補強を進めて行いく。装置の開発など途中の内容もあるので完成まで計画通り進めていく。授業につ いて事後アンケートなどを実施し来年度への検討課題としていきたい。
関連リンク
公共ソリューショングループ
電話番号:026-224-0504
FAX番号:026-224-6233